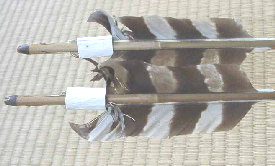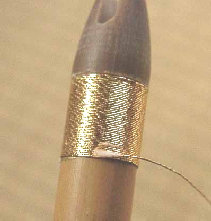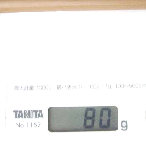羽根は、ゴム系の糊で接着しました。
一番見栄えの良い羽根を走り羽、次を外掛羽にします。
円周をきちんと三分割することと、
羽根をまっすぐに貼ることは なかなか難しい作業です。
失敗したらやかんでお湯を沸かして、
たっぷり蒸気を当てて剥がし、やり直します。
また、蒸気を当てて接着剤を柔らかくすると、
ほんの少しですが位置をずらすこともできます。
次に右のように直径2㎝ほどの紙キャップを被せます。
羽軸の筈側は、この後、適当な長さに切ります。
矧糸は、普通は絹糸を使いますが、
今回は金糸にしました。
従来からある金糸は、芯になっている絹糸がとても弱く、
巻いている途中で簡単に切れてしまい悔しい思いをするので、
芯が化繊の丈夫な糸のものを使う方が便利です。
金糸は表面が金属箔です。
それが剥がれると最初から巻き直しになるので注意します。
また、巻き始めと巻き終わりが滑って止まりにくいので、
上中央と右の写真のように、
ちょっと木工ボンドを付けるのも手だと思います。
糸を巻く際は、箆の反対側をズボンのベルト通しに入れると安定します。
糸を巻いたら、木工ボンドを塗ります。
羽軸のあたりをきちんと塗らないと、
トップコートを塗る際に、裏から染みこんで、
きたなくなってしまいます。
ちなみに昔はゼラチンを使ったようです。
ゼラチンは経年変化で黄色っぽくなるようです。
今回は木工ボンドを2回塗り重ねた後、
カシュー塗料の「透き」で仕上げました。
ただ、節約して古い固まりかけの塗料を使ったので、
ちょっと斑のある仕上がりとなってしまいました。
わずかのお金を惜しんではいけなかったと反省。
縁取りは苦手ですのでしませんでした。
紙のキャップを外すと、羽根はくしゃくしゃになっていますが、蒸気をたっぷり当てて延ばすと元通りに戻ります。
羽中節が光って見えますが、今回の箆の節は、漆芸で使う砕いた貝殻を透明なカシュー塗料に混ぜて埋めています。
鋏で羽根を切り、筈の外周と溝をヤスリで調整し、
板付を入れれば完成です。
鋏は刃渡りが短いとうまく切れません。
筈側からまっすぐ切って幅を決め、
次に元矧側の曲がりを切りますが、
羽根が逃げますのでなかなか難しいものです。
ちょっと芋っぽい仕上がりですので、
そのうち少し調整することにしましょう。
重さは1本あたり40グラムですので、
途中で4グラムほど増えたことになります。
なお、2本の重心のずれは1㎝程度でしたので、
バランス調整はしませんでした。
必要な場合はクスネに砂鉄を混ぜた物を
竹の中に入れて火箸で融かして固定します。
矢の自作工程3